消化器内科とは

口から肛門までは、一本の長い管でつながっており、これを消化管といいます。その長さは約9mともいわれ、食道、胃、小腸、大腸などの器官で構成されています。さらにこの消化管での消化や吸収の働きを助ける、膵臓、肝臓、胆のう等の臓器も含めて消化器といいます。
この消化器で起きたとされる症状や病気について、診察、検査、治療を行うのが消化器内科です。消化器症状といえば、腹痛、嘔吐・吐き気、下痢、便秘などが含まれます。これらの症状というのは、一過性のケースであることが大半です。それでも診察時は、あらゆる可能性を想定し、必要と医師が判定すれば、超音波検査(腹部エコー)や内視鏡検査(胃カメラ、大腸カメラ)を行うなどして、総合的に判断します。
以下のような症状に心当たりがあれば、当診療科をご受診ください。
- お腹の調子がずっと悪い
- 胃で感じる鈍痛に常に悩んでいる
- 吐き気がある
- 胸やけ
- 胃もたれ
- 便通異常(下痢、便秘)がよくみられる
- 便潜血検査で陽性の結果が出た
- 便に血が混じっている(血便)
- 食欲不振である
- 体重が急激に減少している
- 胃の周囲で急な痛みがある
- など
消化器内科で扱う主な疾患
逆流性食道炎
逆流性食道炎とは
胃内で分泌されている胃液(胃酸)、または胃液を含む消化中の食べ物が食道へ逆流してしまうことで、炎症を発症している状態を逆流性食道炎といいます。食道には胃酸から粘膜を守る防除機能がないため胃酸が逆流することがあれば、食道の粘膜は傷つき、炎症を起こすようになるのです。
症状
胸やけ、胸痛、酸っぱい物が込み上げる(呑酸)、嗄声(声がかすれる)、咳などです。病状が進行すると、吐血や黒色便がみられることもあります。
原因
同疾患は、胃から食道への逆流を防ぐ、下部食道括約筋の緩みによって起きるとされています。緩む原因としては、加齢、猫背、肥満、高脂肪食を必要以上に好んで食べる、カフェインの過剰摂取、喫煙のほか、ストレス、ベルト等で腹部を強く締め付けるといったことで発症することもあります。
検査
胃カメラで食道の粘膜の炎症の状態を確認する必要があります。食道の粘膜に炎症がない場合では非びらん性胃食道逆流症(胃酸の逆流や食道の知覚過敏などによって胸やけを感じる状態)の可能性があります。喉の違和感で耳鼻科にて異常がないと言われた場合には逆流性食道炎の症状の可能性があるため、是非胃カメラを受けて下さい。
治療
胃酸分泌抑制剤の内服により症状改善することが多いですが、原因により治療法が異なり、問診より患者さまと相談の上で治療方針を決定させて頂きます。
胃・十二指腸潰瘍
胃・十二指腸潰瘍とは
胃や十二指腸の粘膜が胃酸によって損傷し、内壁がただれるなどして潰瘍がみられている状態をいいます。そもそも胃粘膜は、強力な酸性下に耐えられる構造となっています。ただ何らかの原因で、この構造が壊れてしまうと損傷を受けやすくなります。
症状
みぞおちの痛み(胸やけ)、吐血、黒色便などです。なお潰瘍の状態がひどくなると胃や十二指腸に孔が開くこともあります(胃穿孔、十二指腸穿孔)。
原因
ヘリコバクター・ピロリ菌の感染が最も多いですが、そのほかにもストレス、薬剤の影響(NSAIDs)、喫煙といったことが挙げられます。
検査
胃カメラにて胃・十二指腸の粘膜を確認し炎症、潰瘍、腫瘍などの有無を確認します。組織を採取して病理学的に診断を行う場合もあります。
治療
原因(ピロリ菌除菌、禁煙等による生活習慣の改善 等)によって異なります。ピロリ菌除菌治療は抗生剤2種類と胃酸分泌抑制剤を含めた3種類の内服薬を1週間内服していただきます。
胃がん
胃がんとは
胃粘膜より発生する悪性腫瘍のことを胃がんといいます。胃がんはかつて日本人の死亡原因の第1位でしたが、ピロリ菌感染率が減少しており、現在は肺がん、大腸がんにつぐ第3位です。現在、ピロリ菌が感染は60歳から80歳が中心であり、胃がんが発見される方もこの年代が多いです。
症状
発症して間もなくは、症状が出にくいので気づきにくいという特徴があります。そのため、発症初期で見つかるケースというのは、定期的に行う胃カメラ等の検査によるものが大半です。ある程度まで進行すると、みぞおちの周辺が痛む、胸やけ、吐き気、食欲不振などがみられるようになります。
原因
胃がんの95%以上はヘリコバクター・ピロリ菌(ピロリ菌)感染によるものです。ピロリ菌のほとんどが幼少期に感染し、ピロリ菌が胃粘膜に感染することで胃粘膜が炎症で萎縮することで萎縮性胃炎となり、胃がんが発生しやすくなります。
ただ上記以外にも、食事での塩分の過剰摂取、喫煙、遺伝子異常などもあります。
検査
40歳を過ぎる頃から胃がんは発症率が上昇します。各自治体によっては、40歳以上の方を対象に定期的に胃カメラによる胃がん検診を行っています。早期胃がんの発見は胃カメラが優れており、これまで検診の胃バリウム検査にて何も問題がなかったという方も胃カメラを受けて頂くことをお勧めします。早期に発見し、速やかに治療に努めることができれば、予後は良いとされています。
治療
早期胃がんの治療は胃カメラでの内視鏡治療が主流です。胃がんを早期発見、早期治療することで外科手術を受けることなく、治療後の後遺症もほとんどなく、今まで通りの生活を送ることが可能になります。
ピロリ菌
ピロリ菌とは
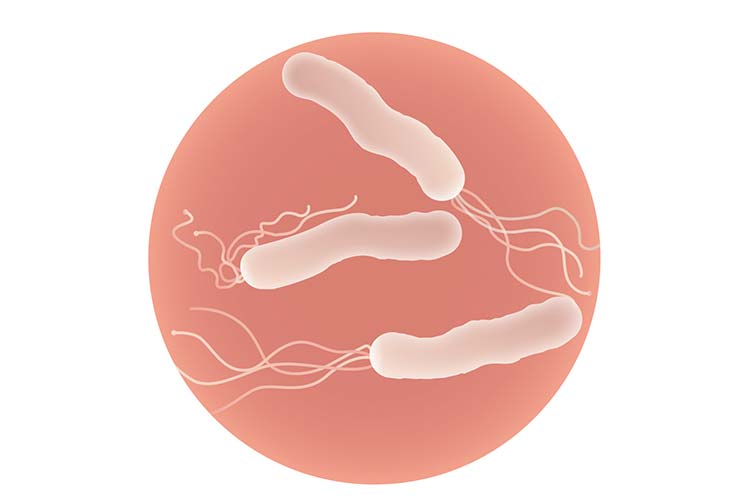
ヘリコバクター・ピロリ胃の中に住み着くらせん状の菌です。以前の日本は衛生環境が悪かったこともあり、大半の方が感染しているということもありましたが、衛生環境も改善し、感染者も減少傾向にあります。
ピロリ菌は、生物が生きにくいとされる強い酸性下にある胃の中で生息しますが、大半は幼少期までに感染することになります。幼少期の胃の中は、成長途上にあってそれほど酸性も強くはないからです。感染経路としては、感染者の大人からの食物の口移しによるものではないかといわれています。胃内に入ったピロリ菌は、ウレアーゼと呼ばれる酵素を分泌します。これによって胃の中の尿素をアンモニアと二酸化炭素に分解し、このアルカリ性のアンモニアで酸を中和させることで、生きながらえるようになるのです。
感染したからといって、すぐに何らかの病気に罹患するということはありません。ただ感染を持続させてしまうことで、慢性胃炎、胃・十二指腸潰瘍、胃がんなどの発症リスクが高くなります。
症状
ピロリ菌に感染している状態であっても症状を認めることは少なく、検診でピロリ菌感染を指摘されることが多いです。ただし、慢性的な胃炎を引き起こせば、胃もたれや胃の不快感、吐き気、食後の腹、食欲不振などが現れるようになります。検査
胃カメラにて現在感染しているかを確認することをお勧めします。
当院では、胃カメラを必要としない下記のピロリ菌検査が出来ます。
抗体検査(血液、尿)
現在または過去のピロリ菌感染を血中の抗体を用いて調べる検査です。
便中抗原検査
糞便中のピロリ菌抗原の有無を調べる検査です。ご自宅で便を採取して、持参ください。
尿素呼気試験
検査薬を服用する前と後の呼気(吐いた息)を採取して調べます。最も信頼性の高い検査ですが、検査時は空腹である必要があり、基本的には除菌治療後の判定時に行います。
治療
ピロリ菌除菌治療は抗生剤2種類と胃酸分泌抑制剤を含めた3種類の内服薬を朝晩2回1週間内服していただきます。内服後約2ヶ月で除菌の成否を判定します。判定方法は尿素呼気試験で行います。1回目での除菌率はおよそ70〜80%といわれています。1回目の除菌が失敗した時は薬の種類を変えて2回目となります。2回目の除菌成功率は90%以上ですが、それでも成功しない場合、3回目、4回目と除菌治療(自費)をくりかえします。
機能性ディスペプシア
機能性ディスペプシアとは
慢性的に胃もたれ、早期満腹感、みぞおちの痛みなどの症状が続いているにもかかわらず、採血や内視鏡検査を行っても症状を説明できる異常が特定できない疾患です。
原因
胃・十二指腸の動き悪くなった場合、胃・十二指腸の知覚過敏が生じている場合、不安やストレスがある場合、ヘリコバクター・ピロリ感染、遺伝的要因、感染性胃腸炎、アルコール・喫煙・不眠などの生活習慣の乱れ、胃の形態(瀑状胃など)など様々な原因があります。
症状
胃の痛みや熱くなる感じ、胃もたれ感、早期満腹感が慢性的に続きます。
検査
問診を行ったうえで血液検査、超音波検査、胃カメラ、CT検査などで異常が認められなかった場合に診断します。
治療
症状に応じて胃酸分泌抑を抑える薬、胃の運動機能を改善させる薬、漢方薬などを内服にて治療を行います。胃に負担をかけない食べ方(食事はゆっくりよくかむように心がける、お腹いっぱい食べない、食べてからすぐ運動しない)が大切です。また、自律神経の調子を整えることも大切です。そのためには、十分な睡眠をとり、ウォーキングなど適度な運動を行い、禁煙することが大事です。
過敏性腸症候群
過敏性腸症候群とは
検査をしても原因を特定することができない、腹痛等腹部の違和感、下痢、便秘などの消化器症状が続いている状態を過敏性腸症候群といいます。20~40代の世代に起きやすいとされ、タイプとしては、下痢型、便秘型、混合型(下痢と便秘を繰り返す)に分かれます。
症状
腹痛、腹部不快感、腹部膨満感、便秘や下痢などがあります。タイプによって症状は異なります。
原因
日頃から感じているとされる、ストレス、不安や緊張などが引き金となって自律神経が乱れ、腸に運動異常がみられることで、腹痛等の症状が繰り返し起きるようになるといわれています。また、感染性腸炎後に発症することもあります。これは、病原菌の感染が引き金となって腸内細菌のバランスの乱れ、過敏性腸炎を発症することもあります。
検査
問診により症状の内容や内服薬、食生活、ストレスの状況などの確認をさせて頂きます。血液検査、大腸カメラなどで他の疾患の可能性を除外した上で診断します。
治療
症状により内服薬による治療を行いますが、ストレスコントロールや生活の見直しも重要とされています。
大腸がん
大腸がんとは
大腸内壁の粘膜から発生する悪性腫瘍のことを大腸がんといいます。良性ポリープが、がん化することが多く、正常な細胞が遺伝子変異を起こすことで、がん細胞に変化して発生するケースもあります。大腸がんの罹患数は2019年の統計では全がん種で第1位になっています。なお大腸がんは、がんが原因で死亡した人の数の中で部位別に見ると女性が第1位、男性でも第2位となっています。これは年別の推移で見ても増加傾向です。
米国はかつて大腸癌死亡率の高い大腸がん大国でしたたが、近年大腸がん死亡率は著明に低下しています。現在、人口が本邦の約3倍である米国の大腸癌死亡者数よりも本邦の大腸癌死亡者数のほうが多いことが明らかになり問題となっています。その原因は検診受診率の差です。米国は45歳を過ぎた国民に大腸内視鏡検査を無償で1回提供しています。便潜血検査による検診とあわせると、大腸がん検診受診率は約70%です。一方、日本では、便潜血検査による検診を行政が進めていますが、その受診率は約20%とはるかに低いです。さらに、便潜血検査が陽性でも約60%の人しか精査(大腸内視鏡検査)を受けていないという事実があります。このように、米国と日本の大腸がん死亡率の差は、この検診受診率の差によると考えられています。大腸カメラの受診率が高ければ大腸がんを減らすことが可能です。
症状
発症して間もなくは自覚症状がありません。その後、病状が進行するにつれて、腹痛、血便、下痢と便秘を繰り返すなどの症状がみられるようになります。
原因
家族歴、肥満、飲酒・喫煙、牛肉の過剰な摂取などにより、がんの前の状態であるポリープの発生を上昇させます。
検査
腹部超音波検査、大腸CTなど大腸カメラ以外の検査はありますが、いずれも確定診断には至らないため大腸カメラが推奨されます。
治療
大腸がんは、早期(ステージ0もしくは1)に発見することができれば、治癒率は高いとされています。また、がんの前の状態である大腸ポリープを切除することで大腸がんの発生を防ぐことが可能です。
自覚症状がないので気づきにくいかもしれませんが、40歳を過ぎる頃から罹患率は上昇し、各自治体では40歳以上の方を対象に大腸がん検診を行います。対象者の方はできるだけ受けるようにしましょう。
便通異常
便通異常とは
正常とされる便通でない状態にあることを便通異常といいます。この場合、便秘や下痢などが起こっています。
そもそも便秘とは、便が硬くなって排便がしにくい、排便回数が週3回未満にある場合にその可能性が高いとされています。一方の下痢は、水分が多く含まれている便が何度も繰り返される状態をいいます。一過性のケースもあれば、慢性的に起きていることもあります。また人によっては、この便秘と下痢を繰り返しているということもあります。
原因
不摂生な生活習慣(生活リズムが不規則、運動不足、食生活の影響(高脂肪食の過剰摂取、食物繊維不足 等) など)、ストレス、何らかの病気(過敏性腸症候群、大腸がん、感染性胃腸炎、潰瘍性大腸炎、腸閉塞症 等)を発症しているといったことが考えられます。
検査
診察の結果、必要に応じて、腹部超音波検査(腹部エコー)、内視鏡検査、CT検査、血液検査などを行い、診断をします。
治療
原因に合わせた治療を行います。
